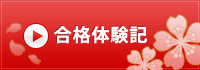現役合格おめでとう!!
2025年 津田沼校 合格体験記

早稲田大学
政治経済学部
経済学科
茂木柊志 くん
( 昭和学院秀英高等学校 )
2025年 現役合格
政治経済学部
僕は高校2年生の2月に東進に入学しました。そのときはまだ勉強する習慣がついてなく、自分の志望校も決まっていませんでした。東進に入学したときに志望校を決めて入試までの1年間の計画をしっかり立てて、受験勉強をスタートしました。最初に受けた1月の共通テスト同日体験受験では国数英で4~5割程度で、最初はこんなものかと思ってコツコツ勉強をしました。
初めに高速マスター基礎力養成講座で英単語を覚えました。そのあと飛翔という英文読解の講座を受講して、英文を読めるようにしました。英語と数学は7月の終わりころまで受講とその復習を繰り返していました。夏休みで志望校の過去問を初めて解き、合格最低点の半分もとることが出来ずにショックを受けました。ですが8月の共通テスト本番レベル模試で数学で7割を超え、英語も6割を超えることが出来て、自分の勉強してきたことは間違っていないと思い、その後もモチベーションを保ちながら勉強を続けることが出来ました。
夏休みが明けてからは志望校別単元ジャンル演習講座に取り組みました。そこで大量の入試レベルの演習を積むことで入試問題に慣れることが出来ました。11月の記述模試では国数英で過去最高点を取り、やる気が出て勉強に取り組むことが出来ました。12月1月は共通テスト対策をして、共通テスト本番で国数英で目標だった8割をとることが出来ました。
共通テストが終わってからの1か月は最後の追い込みで今までで1番勉強しました。具体的には私大の志望校の過去問を科目にもよりますが、平均して8~10年分解いて、各志望校各学部の独特の入試形式に慣れました。第1志望だった大学の過去問は夏休みに10年分解いていましたが、最近5年分は2周解きました。また自分が使っていた参考書を何度も読み返しました。最後の1か月の追い込みのおかげで、共通テストからさらに成績を伸ばし、志望校に合格することが出来ました。
僕が受験生として1年間で学んだことは、質を高めるためには量をたくさんこなし続けることが大切だということです。また担任の先生や担任助手の方、チームミーティングのメンバーともコミュニケーションをとることで、モチベーションを保つことが出来ました。この1年間で僕は成長できたと思います。
初めに高速マスター基礎力養成講座で英単語を覚えました。そのあと飛翔という英文読解の講座を受講して、英文を読めるようにしました。英語と数学は7月の終わりころまで受講とその復習を繰り返していました。夏休みで志望校の過去問を初めて解き、合格最低点の半分もとることが出来ずにショックを受けました。ですが8月の共通テスト本番レベル模試で数学で7割を超え、英語も6割を超えることが出来て、自分の勉強してきたことは間違っていないと思い、その後もモチベーションを保ちながら勉強を続けることが出来ました。
夏休みが明けてからは志望校別単元ジャンル演習講座に取り組みました。そこで大量の入試レベルの演習を積むことで入試問題に慣れることが出来ました。11月の記述模試では国数英で過去最高点を取り、やる気が出て勉強に取り組むことが出来ました。12月1月は共通テスト対策をして、共通テスト本番で国数英で目標だった8割をとることが出来ました。
共通テストが終わってからの1か月は最後の追い込みで今までで1番勉強しました。具体的には私大の志望校の過去問を科目にもよりますが、平均して8~10年分解いて、各志望校各学部の独特の入試形式に慣れました。第1志望だった大学の過去問は夏休みに10年分解いていましたが、最近5年分は2周解きました。また自分が使っていた参考書を何度も読み返しました。最後の1か月の追い込みのおかげで、共通テストからさらに成績を伸ばし、志望校に合格することが出来ました。
僕が受験生として1年間で学んだことは、質を高めるためには量をたくさんこなし続けることが大切だということです。また担任の先生や担任助手の方、チームミーティングのメンバーともコミュニケーションをとることで、モチベーションを保つことが出来ました。この1年間で僕は成長できたと思います。

早稲田大学
社会科学部
社会科学科
熊手佑弥 くん
( 市川高等学校 )
2025年 現役合格
社会科学部
僕は親や友人、担任の先生と担任助手の方に恵まれ、最後まで勉強を続けることができました。僕が東進に入ったのは高1の1月のことで割と早めだったと思います。当時の僕は、学校の友人がみんな塾に行っていると聞いて焦っており、親に頼んで体験授業を受けさせてもらったのが東進でした。僕は部活動を優先したいという理由で東進への入学を決めました。
高2の10月に行われた学校での三者面談で勉強へのモチベーションが一気にあがりました。僕の学校では11月の修学旅行の直後からみんなが本腰を入れてきたので、僕もそれに乗っかりうまくスタートダッシュを切ったと思います。そして1月に入り、東進による毎年恒例の共通テスト同日体験受験で英数がどちらも75パーセントくらいとれたのでそれほど心配していませんでした。幸いにも、僕の学校の友達は受験に向けて頑張る人が多かったので、自分も気持ちを切らさずにやり切れました。
いくつかアドバイスがあります。ひとつは英数を高3になる前に共通テストなら9割とれるくらいの力をつけておきましょう。2つ目は理社と情報をなめるなということです。僕はほかの人に比べて特別センスがなかったのもあると思いますが、夏に入る前にどれか1教科だけでも完璧にしておいたほうがいいです。
最後は、結局メンタルの強いやつが勝つということです。僕は模試の成績がひどすぎて、受験校すべてがチャレンジ枠みたいになってしまいましたが、「まあ、いけるっしょ」くらいの気持ちで試験に臨みました。これは決して楽観的になれということではなく、そう思えるくらいに努力をしろということです。僕は部活も頑張っていたので、それも直前期のメンタルにいい影響を与えたとおもいます。将来は半沢直樹のように銀行員か、金融関係の仕事に就きたいと考えています。受験で頑張った経験を活かして就活なども頑張りたいです。
高2の10月に行われた学校での三者面談で勉強へのモチベーションが一気にあがりました。僕の学校では11月の修学旅行の直後からみんなが本腰を入れてきたので、僕もそれに乗っかりうまくスタートダッシュを切ったと思います。そして1月に入り、東進による毎年恒例の共通テスト同日体験受験で英数がどちらも75パーセントくらいとれたのでそれほど心配していませんでした。幸いにも、僕の学校の友達は受験に向けて頑張る人が多かったので、自分も気持ちを切らさずにやり切れました。
いくつかアドバイスがあります。ひとつは英数を高3になる前に共通テストなら9割とれるくらいの力をつけておきましょう。2つ目は理社と情報をなめるなということです。僕はほかの人に比べて特別センスがなかったのもあると思いますが、夏に入る前にどれか1教科だけでも完璧にしておいたほうがいいです。
最後は、結局メンタルの強いやつが勝つということです。僕は模試の成績がひどすぎて、受験校すべてがチャレンジ枠みたいになってしまいましたが、「まあ、いけるっしょ」くらいの気持ちで試験に臨みました。これは決して楽観的になれということではなく、そう思えるくらいに努力をしろということです。僕は部活も頑張っていたので、それも直前期のメンタルにいい影響を与えたとおもいます。将来は半沢直樹のように銀行員か、金融関係の仕事に就きたいと考えています。受験で頑張った経験を活かして就活なども頑張りたいです。

慶應義塾大学
理工学部
学門C(情報・数学・データサイエンス)
平島優輝 くん
( 船橋高等学校 )
2025年 現役合格
理工学部
入学時点から自分の学力に合う授業をとれることから、2年生の春ごろに東進への入学を決めました。志望校へ向けて勉強する中で、東進のコンテンツでは「過去問演習講座」がとても役立ったと思っています。記述答案を提出した翌日から解説授業をみることができ、添削答案は5日以内には返却されます。解説授業はおおよそ市販の過去問よりも詳しく、何より自分の点数が可視化されることがモチベーションにつながりました(自分は東進の過去問と市販の過去問とで発想・解答例等を見比べていました。こういった使い方もおすすめです)。
来年度以降に受験をするみなさんには「基礎をおろそかにするべきではない」ということを伝えたいです。過去問を解き志望校の出題傾向をつかみ、その後の学習の見通しをたてることは重要ですが、秋以降は実際に出題されるような難易度の問題を解かなければいけないというわけではありません。とくに、自分でやると決めた講座や参考書についてははじめからおわりまでしっかりと取り組んだほうがよいです。やはり、基礎が網羅できているかいないかで体系的な理解の構築には差が生じてきます。(自分はこの点がうまくいかず、発展事項に自分のもっている知識でアプローチしていけるようになるのは、本試もだいぶ近づいてきてからになってしまいました。)みなさんの健闘を祈っております!
来年度以降に受験をするみなさんには「基礎をおろそかにするべきではない」ということを伝えたいです。過去問を解き志望校の出題傾向をつかみ、その後の学習の見通しをたてることは重要ですが、秋以降は実際に出題されるような難易度の問題を解かなければいけないというわけではありません。とくに、自分でやると決めた講座や参考書についてははじめからおわりまでしっかりと取り組んだほうがよいです。やはり、基礎が網羅できているかいないかで体系的な理解の構築には差が生じてきます。(自分はこの点がうまくいかず、発展事項に自分のもっている知識でアプローチしていけるようになるのは、本試もだいぶ近づいてきてからになってしまいました。)みなさんの健闘を祈っております!

東京理科大学
薬学部
薬学科
川合夏蓮 さん
( 東邦大学付属東邦高等学校 )
2025年 現役合格
薬学部
私は、中学受験以来勉強習慣がなく、定期テストの前だけ少し勉強して、将来の事は何も考えずに受験生になればやる気も出るだろうし、きっとやればできるだろうと思って過ごしていました。
しかし、高2になって最初の数学の小テストで私だけ全く手が動かず、初めて焦りを感じました。そこから1学期の定期考査に向けて自分なりに勉強しましたが、家ではあまり集中できず、結果も酷かったため、このままではまずいと思い、高2の7月に東進に入学しました。
入学時の面談では、私の現状と志望校の乖離を目の当たりにし、焦りは募るばかりでしたが、面談と合格設計図のおかげで、受験までの流れをつかめ、何をすればよいのかが明確になりました。それをチームミーティングで1日単位で受講や問題集の計画に落とし込みこなすことができました。
家では全く集中できない私でも、東進では面白い授業の受講と計画していた問題集をやっているとすぐに時間がたっていました。高2の夏休みは毎日12時間ほど勉強していたと思いますが、全く苦ではなく、むしろ今まで分からなかったことが理解できることが楽しかったです。ここで長時間の勉強の習慣がついたことが受験生になってから役立ちました。
しかし、受験が近づくにつれモチベーションが保てず集中できなかったり、成績が思うように上がらなかったり、周りの友達の成績と比べたりして落ち込んでいました。そんな時にチームミーティングで他校の生徒の人と話したり、担任助手の方のお話を聞いたりすることで、またやる気がでました。
また、成績がよく、ずっと集中して勉強している友達と話すとその子にもモチベーションの波があることを知り、多少の波は気にせずとにかく毎日続けることを学びました。私は頑張るということだけで済ませてしまうことが多かったのですが、問題点は何で、何をどう頑張るのか具体的にすることが大切だということを学びました。
実際、最後共通テスト本番レベル模試で目標点まで100点足りず、かなり焦りましたが、やることを書き出し、優先順位を立て勉強することで、本番では130点あげることができました。最後まで諦めないことも重要です。
これから受験を迎える方は、辛くなって逃げたくなる日もあると思いますが、私が全く勉強をしていなかった時に不安を感じたことが全くなかったことから分かるように、努力しているから不安を感じる事を忘れず、私よく頑張ってるな、努力しているなと自分を褒めて、適度にリフレッシュしつつ受験生活を送ってください。毎日コツコツ続ければ最後は報われます。皆さんが志望校合格できるよう願ってます。
しかし、高2になって最初の数学の小テストで私だけ全く手が動かず、初めて焦りを感じました。そこから1学期の定期考査に向けて自分なりに勉強しましたが、家ではあまり集中できず、結果も酷かったため、このままではまずいと思い、高2の7月に東進に入学しました。
入学時の面談では、私の現状と志望校の乖離を目の当たりにし、焦りは募るばかりでしたが、面談と合格設計図のおかげで、受験までの流れをつかめ、何をすればよいのかが明確になりました。それをチームミーティングで1日単位で受講や問題集の計画に落とし込みこなすことができました。
家では全く集中できない私でも、東進では面白い授業の受講と計画していた問題集をやっているとすぐに時間がたっていました。高2の夏休みは毎日12時間ほど勉強していたと思いますが、全く苦ではなく、むしろ今まで分からなかったことが理解できることが楽しかったです。ここで長時間の勉強の習慣がついたことが受験生になってから役立ちました。
しかし、受験が近づくにつれモチベーションが保てず集中できなかったり、成績が思うように上がらなかったり、周りの友達の成績と比べたりして落ち込んでいました。そんな時にチームミーティングで他校の生徒の人と話したり、担任助手の方のお話を聞いたりすることで、またやる気がでました。
また、成績がよく、ずっと集中して勉強している友達と話すとその子にもモチベーションの波があることを知り、多少の波は気にせずとにかく毎日続けることを学びました。私は頑張るということだけで済ませてしまうことが多かったのですが、問題点は何で、何をどう頑張るのか具体的にすることが大切だということを学びました。
実際、最後共通テスト本番レベル模試で目標点まで100点足りず、かなり焦りましたが、やることを書き出し、優先順位を立て勉強することで、本番では130点あげることができました。最後まで諦めないことも重要です。
これから受験を迎える方は、辛くなって逃げたくなる日もあると思いますが、私が全く勉強をしていなかった時に不安を感じたことが全くなかったことから分かるように、努力しているから不安を感じる事を忘れず、私よく頑張ってるな、努力しているなと自分を褒めて、適度にリフレッシュしつつ受験生活を送ってください。毎日コツコツ続ければ最後は報われます。皆さんが志望校合格できるよう願ってます。

三重大学
工学部
総合工学科/電気電子工学コース
川浪月也 くん
( 千葉英和高等学校 )
2025年 現役合格
工学部
僕は高校2年生の終わりごろに、春の新年度特別招待講習へ参加したのがきっかけで東進に入りました。それ以前の勉強といえば定期テスト前の復習くらいであったものですから、基礎がボロボロで3年の初めのころは基礎固めに全力を注いでいました。
東進に入って1番役に立ったものは過去問演習講座大学入学共通テスト対策や第一志望校対策演習講座の解説授業で、「問題を解く→解説を聞く→少し経ったら復習」の周期を延々と繰り返していました。また、受験数学Ⅲで、声や喋り方が特徴的でなおかつ教え方も上手く、授業の内容が頭の中にすっとはいってきて、まったく授業内容を忘れなかったです。そのおかげもあってか数学の点数は目に見えて伸びていきました。
東進の良いところは、担任の先生がさぼっていると注意してくれることです。僕は本質的に怠け者ですから、「担任の先生のおかげで無事に高校3年生での受験勉強をやり切れたと言っても過言ではない」と、言い切れる程に僕の受験勉強で重要な物でした。
大学では興味のあった電気電子の分野を学ぶので、探求心を忘れずにこれからも勉学に励んでいきたいと思います。
東進に入って1番役に立ったものは過去問演習講座大学入学共通テスト対策や第一志望校対策演習講座の解説授業で、「問題を解く→解説を聞く→少し経ったら復習」の周期を延々と繰り返していました。また、受験数学Ⅲで、声や喋り方が特徴的でなおかつ教え方も上手く、授業の内容が頭の中にすっとはいってきて、まったく授業内容を忘れなかったです。そのおかげもあってか数学の点数は目に見えて伸びていきました。
東進の良いところは、担任の先生がさぼっていると注意してくれることです。僕は本質的に怠け者ですから、「担任の先生のおかげで無事に高校3年生での受験勉強をやり切れたと言っても過言ではない」と、言い切れる程に僕の受験勉強で重要な物でした。
大学では興味のあった電気電子の分野を学ぶので、探求心を忘れずにこれからも勉学に励んでいきたいと思います。